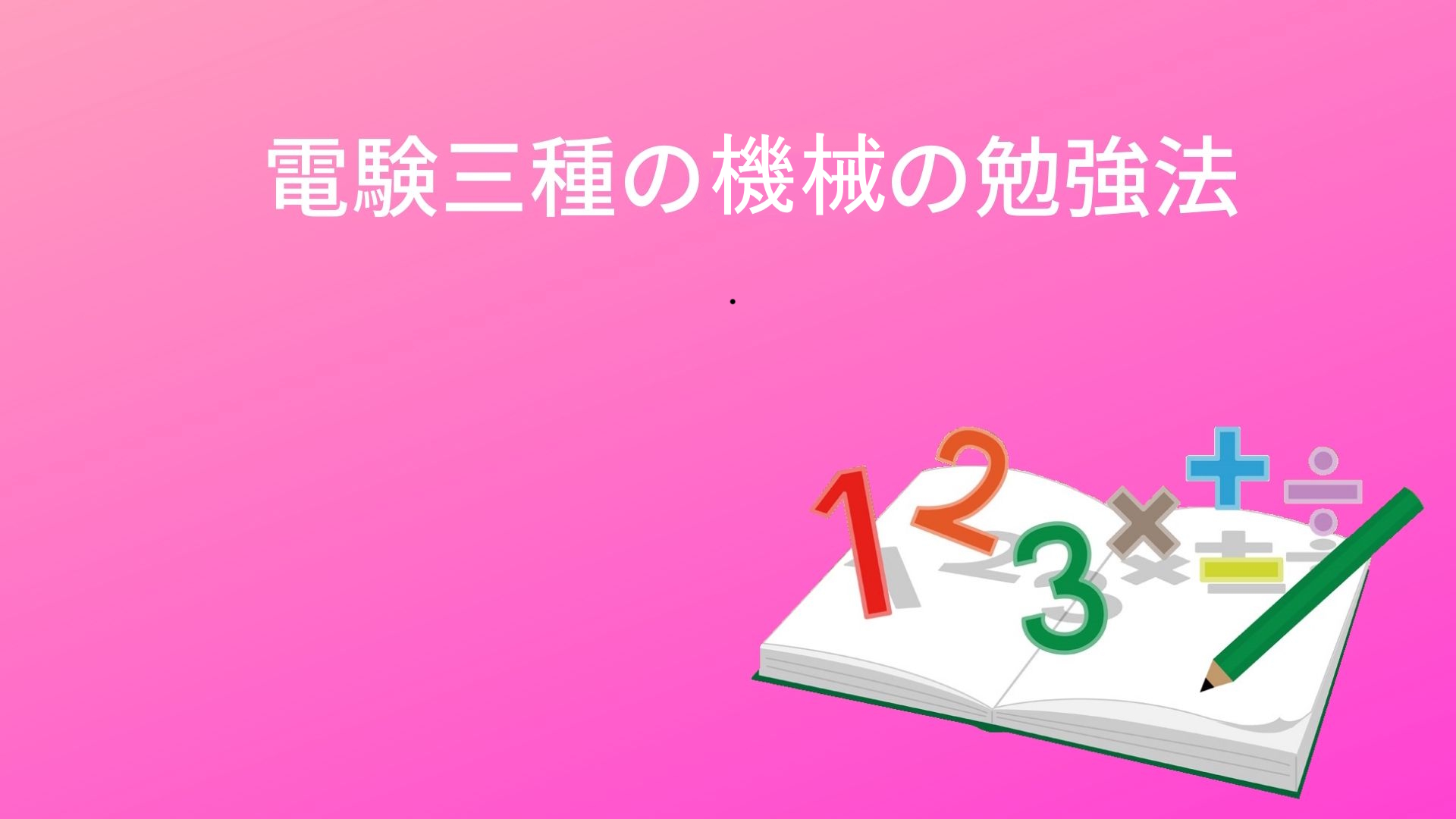このページでは、電験三種の機械科目の正しい勉強法を紹介しています。電験三種の試験に合格するには、要点を押さえた効率的な勉強法がポイントになります。 試験を知り、効率よく合格できる学習戦略を立てましょう。
電験三種の機械について
電験三種の機械科目は、電動機、発電機、変圧器、電気機器、電動機応用、パワーエレクトロニクス、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理などの分野より出題されます。幅広い知識が必要となりますので、試験対策が難しくなることがあります。
機械科目は、電動機の回転原理や変圧器の磁束の動きなど、具体的な装置の動作について理解していないと解けない問題が多いです。実際の機械がどのように機能するのか、イメージしながら学習する必要があります。また、機械科目は、電動機や発電機、変圧器などの性能や動作に関する計算問題が多く出題されます。そのため、計算式や法則の理解が必須となります。
電験三種の機械科目
このサイトでは、電験三種の機械について、単元ごとに勉強がしやすいように解説と過去問題を1ページごとにまとめています。
直流機
同期機
誘導機
変圧器
電気機器
電動機応用
パワーエレクトロ二クス
照明
電熱
電気化学(電池)
自動制御
情報
電験三種の機械の試験について
電験三種の機械科目の試験は、A問題とB問題に分かれており、A問題は基本問題、B問題は応用問題(ほぼ計算問題)となっています。A問題は14問出題され、B問題は4問で設問が2つに解かれています。B問題は、全4問のうち2問は必ず解答する必修問題で、残り2問のうち1問を選択します。つまり、電験三種の機械では、20個の問題に解答することとなります。
1問あたりの点数は5点で、合格基準点は60点ですが、合格率の高い(簡単な)年と低い(難しい)年の差が激しいといった印象です。そのため、合格点が60点を割ることが、結構あります。
電験三種の機械科目は、計算問題が60%、知識を問う問題が40%の割合ぐらいで出題されます。計算問題は、問題文だけではイメージしにくいため、図を描くことで視覚的に理解する必要があります。回路図やベクトル図を自分で書けるようになることが合格の鍵になります。
電験三種の機械の勉強法
電験三種の機械の出題傾向は、だいたい次のようになります。
- 直流機 … 2問(10点)程度
- 誘導機 … 2問(10点)程度
- 同期機 … 2問(10点)程度
- 変圧器 … 2問(10点)程度
- 電気機器全般 … 2問(10点)程度
- 電動機応用 … 1問(5点)程度
- パワーエレクトロ二クス … 3問(15点)程度
- 電熱 … 1問(5点)程度
- 照明 … 1問(5点)程度
- 電気化学(電池) … 1問(5点)程度
- 自動制御 … 1問(5点)程度
- 情報 … 2問(10点)程度
各分野の出題配分は、年によって多少の変動はありますが、だいたい同じような配分で出題されています。毎年、半分が半分が四機(直流機・誘導機・同期機・変圧器)に関する問題です。それに、パワーエレクトロ二クスを加えると、ほぼ合格基準(60%)に達することになります。
合格するためのコツは、まずは、易しくて重要度の高い問題を繰り返し解きましょう。そうすることで、問題のパターン化が見えてきます。パターン化が見えれば、出題頻度の高い問題を繰り返しときましょう。最後の仕上げは、難易度の高い問題を解き、実力アップを図りましょう。